大分県立入試の数学について傾向分析・取り組むべき学習方法をお伝えしていきます。
【数学】大分県立入試の傾向

大分県立入試の数学は毎年出題される単元が決まっています。
「小問集合」「関数」「空間図形」「平面図形」は必ず出される単元です。
一方で「資料の整理」「一次関数」「規則性」「確率」は超頻出単元です。
| 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 | 2018年度 | 2017年度 | |
| 大問1(20) | 小問集合 | 小問集合 | 小問集合 | 小問集合 | 小問集合 |
| 大問2(8) | 関数(グラフ) | 資料の整理・確率 | 関数(グラフ) | 関数(グラフ) | 関数(グラフ) |
| 大問3(8) | 資料の整理・一次関数 | 関数(グラフ) | 数の規則性 | 資料の整理・確率 | 一次関数 |
| 大問4(8) | 数の規則性 | 一次関数 | 方程式 | 一次関数 | 数の規則性 |
| 大問5(8) | 空間図形 | 空間図形 | 空間図形 | 空間図形 | 空間図形 |
| 大問6(8) | 平面図形 | 平面図形 | 平面図形 | 平面図形 | 平面図形 |
過去5年間の平均点は、受験者平均点は33.46点でした。
- 令和3年度 33.0 点
- 令和2年度 31.9 点
- 平成31年度 24.7 点
- 平成30年度 23.8 点
- 平成29年度 28.4 点
- 平成28年度 25.5 点
直近年度は平均点が30点を超えており、易しめになっています。
大分県立入試【数学】の大問別攻略方法
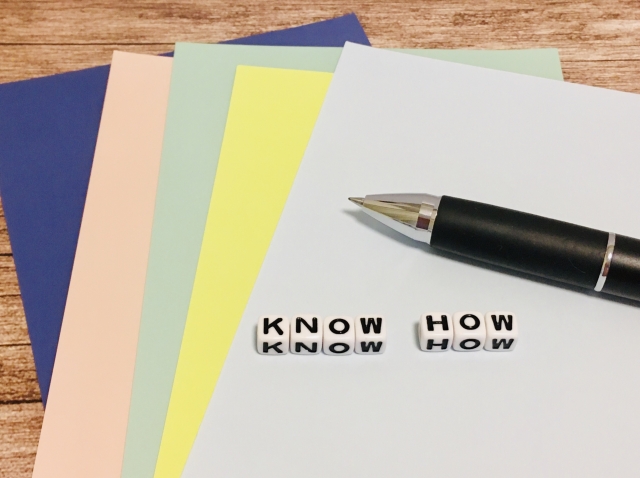
全体の特徴
小問集合のほかに単元ごとの大問が5題あります。
各大問が3~4題ほどしかないので、1題でも間違えれば正答率が落ちてしまいます。
大問によっては完答を求められる形式となっています。
出題パターンが決まっているので、大問ごとに重点的に対策をすれば良いでしょう。
小問集合
| 難易度 | やや簡単 |
|---|---|
| 時間配分 | 10分 |
| 目安点数 | 18点以上/20点 |
小問集合の傾向
小問集合は計算問題を軸とした大問です。
以下に各年の傾向を見ていきましょう。
| 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 | 2018年度 | 2017年度 | |
| 計算問題 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 2次方程式 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 作図 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 方程式 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 角度 | 〇 | 〇 | |||
| 確率 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 平方根 | 〇 | 〇 | |||
| 円周角 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 空間図形 | 〇 | ||||
| 資料の整理 | 〇 | 〇 |
各2点ずつの小問集合です。
簡単な計算問題で10点。残りの10点は各単元からランダムで出されます。
小問集合の対策
「2次方程式」「作図の問題」が必ず出されます。
加えて「方程式」「角度」「確率」「平方根」「円周角」が頻出単元で、過去5年間で3題も出されています。
いずれにせよ計算問題が主体の必答大問です。
時間をかけてでも全問正解を目指して確実に解いていきましょう。
関数(グラフ)
| 難易度 | 標準 |
|---|---|
| 時間配分 | 8分以内 |
| 目安点数 | 5点以上/8点 |
関数(グラフ)の傾向
二次関数・一次関数のグラフを使った融合問題が出されます。
毎年、問題は3題しか出題されません。
(1)(2)が基本問題で(3)が標準~応用問題です。
| (1) | (2) | (3) | |
| 配点 | 2点 | 3点 | 3点 |
また、関数(グラフ)は設問の出題傾向もハッキリしています。
(1)は傾きを求める問題:2点
(2)は式や座標を求める問題:3点
(3)は面積を活用する問題:3点
関数(グラフ)の対策
(1)(2)は基本問題なので確実に取りにいきましょう。
(1)の傾きを求める問題は二次関数だけでなく、反比例の傾きを求める問題も出されています。基本的な式の作り方は復習しておきましょう。
(3)は配点が3点ですので落とせば大問の正答率が一気に落ちます。応用問題でなければ得点したいところです。
面積を求める問題は「等積変形」を活用するパターンが多いので、該当問題の見直しは必須だと言えるでしょう。
一次関数
| 難易度 | やや難 |
|---|---|
| 時間配分 | 10分以内 |
| 目安点数 | 75%以上 |
一次関数の傾向
過去5年間で4回も出題されている頻出の大問です。
一次関数の問題条件も毎回ちがいます。
| 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 | 2018年度 | 2017年度 | |
| 単元 | 道のり・速さ・時間 | 料金 | – | ダイヤグラム | 水そう |
関数(グラフ)の対策
いずれも良く出るタイプのパターン問題です。
一次関数の文章題をひと通り解いておけば問題ないでしょう。
表にグラフを書き入れる問題も出題されるため、グラフから関数式を作る力はつけておきましょう。
資料の整理
| 難易度 | 標準 |
|---|---|
| 時間配分 | 5分以内 |
| 目安点数 | 75%以上 |
資料の整理は過去5年間で4回出題されています。
全体の配点は4点ほどでヒストグラムや度数分布表を基にした問題が出されます。
特に差が付きやすいのが(2)の理由説明問題。記述・記号を中心とした問題で読解力を問われます。
確率
| 難易度 | 標準 |
|---|---|
| 時間配分 | 5分以内 |
| 目安点数 | 75%以上 |
過去5年間で3回出されている頻出単元です。
しかし確率が単独で大問として出ることは今のところありません。
「硬貨」や「サイコロ」、「玉を取り出す」問題など出題パターンは毎年違います。
いずれも樹形図や六々表を記せば順当に正解にたどり着ける問題です。
平面図形
| 難易度 | 標準 |
|---|---|
| 時間配分 | 10分以内 |
| 目安点数 | 80%以上 |
平面図形の傾向
| 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 | 2018年度 | 2017年度 | |
| 出題分野 | ひし形、相似 | 相似、円周角 | 平行四辺形、相似 | 平行四辺形、合同、相似 | 相似、円周角 |
平面図形は「三角形」「円」「平行四辺形」など複数の図形を組み合わせて出されます。
設問は3題で毎年「相似」を活用して解く問題が必ず出されます。
平面図形の対策
証明問題が必ず1題出題されます。
証明の内容も「三角形の相似」「三角形の合同」「平行四辺形」など多岐に渡ります。
ひと通り平面図形の証明問題は入試直前に見直しておきましょう。
また、他の設問についても「相似」を使って辺の長さや面積を出す問題が頻出です。
平面図形の対策として最も重点的に行うべきは「相似」だと言えるでしょう。
空間図形
| 難易度 | やや難 |
|---|---|
| 時間配分 | 10分以内 |
| 目安点数 | 70%以上 |
空間図形の傾向
| 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 | 2018年度 | 2017年度 | |
| 出題分野 | 三角すい、三平方、相似 | 四角すい、球、三平方 | 円すい、三平方 | 三角すい、四角すい、三平方 |
空間図形は毎年出題される図形が違います。「三角すい」「四角すい」「円すい」など錐に関する図形が頻出です。
設問は3~4題で「三平方の定理」を活用して解く問題が必ず出されます。
空間図形の対策
空間図形だけあって体積を求める問題は要チェックです。
公式に基づいて順当に体積を出す設問ではなく、「高さ」を三平方の定理で求めるなど数学的思考が必要です。
三平方の定理を活用した空間図形問題を重点的に演習しておきましょう。
大分県立入試【数学】に向けて絶対するべき3つのこと

- 全範囲の小問演習
- 関数問題の集中対策
大分県立入試は各大問の問題数が少なく、1題でも落とせば得点を大きく落とします。
とは言っても各大問の(1)(2)は易しめの設問です。
小問集合対策でも十分に対応できるでしょう。
もし不安があれば、入試直前に全範囲の小問演習をやっておく事をおススメします。
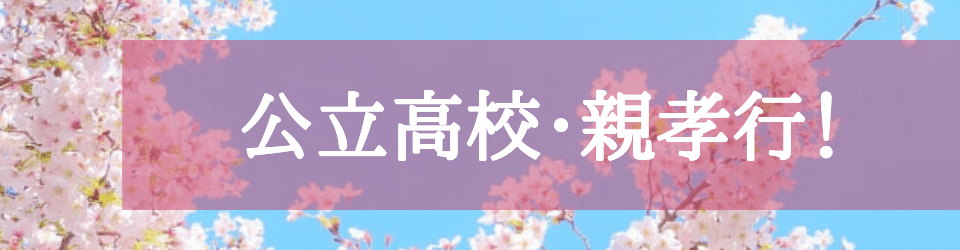


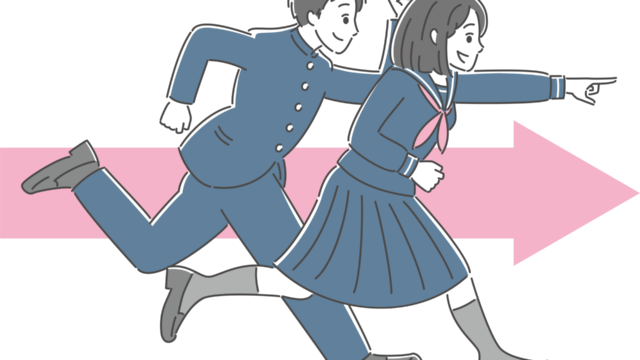

.png)
.jpg)

-640x360.png)



